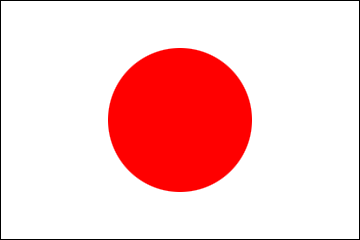当館管轄区域概観
各連邦構成主体概観
| 地域名 | 面積 (km2) |
人口 (人) |
日本との時差 (時間) |
首都 |
|---|---|---|---|---|
| ハバロフスク地方 | 78万7600 | 127万3488 | -1 | ハバロフスク市 |
| ユダヤ自治州 | 3万6300 | 14万4428 | -1 | ビロビジャン市 |
| アムール州 | 36万1900 | 75万3046 | 0 | ブラゴヴェシチェンスク市 |
| サハ共和国(ヤクーチヤ) | 308万3500 | 100万6561 | 0 | ヤクーツク市 |
| ザバイカル地方 | 43万1900 | 98万3838 | 0 | チタ市 |
| ブリヤート共和国 | 35万1300 | 97万1139 | +1 | ウラン・ウデ市 |
| イルクーツク州 | 77万4800 | 232万2292 | +1 | イルクーツク市 |
| 管轄区域データ集 (PDF) | ||||
ハバロフスク地方
- 知事:
- ドミトリー・デメシン
- 議会議長:
- ニコライ・シェフツォフ
- ハバロフスク市長:
- セルゲイ・クラフチュク
- 地勢:
- 東はオホーツク海に面しており、川や湖の多い山がちな領土である。南北の長さが約1800kmあるため、多様な動植物が見られる。南部で約900kmにわたり中国と国境を接している。
- 沿革:
- ハバロフスクの名は、17世紀中頃にこの地を探検したロシアの探検家エロフェイ・ハバーロフにちなんでいる。1858年、ロシア帝国と清国との間で結ばれたアイグン条約によりこの地がロシア領に編入され、同年、現在のハバロフスク市の位置に国境守備隊の哨戒所が設けられたことを契機に都市の建設が始まり、1893年に現在の名称であるハバロフスクとなった。
第二次世界大戦後、シベリア抑留の中心地の一つとして多くの日本人が強制労働に従事し、これらの日本人が残した建築物は現在も各地で見ることができる。
ソ連時代においては、中国と国境を接する軍事的要塞の地として(当地には東部軍管区司令部が存在)、また、豊富な天然資源を背景とした原材料の供給地として、軍需産業を中心に発展してきた(造船所、航空機製造工場などがある)。
現在ハバロフスク市には、日本と中国の2ヶ国が総領事館を置いている。
ユダヤ自治州
- 知事:
- マリヤ・コスチュク
- 議会議長:
- ロマン・ボイコ
- ビロビジャン市長:
- マクシム・セミョノフ
- 地勢:
- 極東地域の南に位置し、アムール川を挟んで中国(黒竜江省)と550kmに亘って国境を接している。
- 沿革:
-
19世紀末、シベリア鉄道の建設開始と共に多くの建設労働者が流入し、1928年、この地区がユダヤ人入植地に指定されるとユダヤ人が移住するようになった。1930年に極東地方の一部としてビロビジャン地区が創設され、34年の改編でユダヤ自治州が誕生した。
38年、極東地方がハバロフスク地方と沿海地方に分割されたことに伴い、同自治州は再びハバロフスク地方に編入されたものの、1991年にロシア連邦の独立した構成主体となって現在に至る。
州都ビロビジャンは、1912年創設されたアムール鉄道のチホニカヤ駅から発展した。この駅に、1928年に最初のユダヤ人移住者600人がウクライナやベラルーシから到着した。1931年、駅はビロビジャンと改名され、37年には市となった。ビロビジャンという名称は、州を流れる2つの河川ビラ川とビジャン川にちなんで名付けられた。
アムール州
- 知事:
- ヴァシリー・オルロフ
- 議会議長:
- コンスタンチン・ジャコノフ
- ブラゴヴェシチェンスク市長:
- オレグ・イマメエフ
- 地勢:
- ロシア連邦の南東に位置し、北はスタノヴォイ山脈に、南はアムール川に囲まれている。また、南はアムール川を挟んで中国と1246kmもの長い国境を接している。
- 沿革:
-
ロシア人がアムール川流域を開拓し始めたのは17世紀前半のことで、その代表格がポヤコフ、ハバロフ等の探検家達であった。その後、アムール川上流域にコサックが移住し、1858年12月、皇帝の勅令によりアムール州が創設された。コサックに続いて、ロシア中央部から農民達が移住するようになり、20世紀初めに鉄道建設が始まったことがこの地域を大きく発展させることとなった。
ロシア革命(1917年)後、アムール州は、アムール県となったり、極東共和国あるいはハバロフスク地方の一部となったりしたが、1948年、ハバロフスク地方から分離され、再び単独のアムール州となった。
サハ共和国(ヤクーチヤ)
- 首長:
- アイセン・ニコラエフ
- 議会議長:
- アレクセイ・エレメエフ
- ヤクーツク市長:
- エフゲニー・グリゴリエフ
- 地勢:
-
ロシア全土の約18%を占め、かつロシアの連邦構成主体の中で最大の面積を誇る。共和国内には3つの時間帯が存在している。
国土のほぼ全域が永久凍土(地下500メートル以上)に覆われている。また、国土の80%がタイガ地帯で、針葉樹林に覆われている。
また、共和国を南北に流れるレナ川をはじめ、多くの河川が存在する。
- 沿革:
-
ヤクート人の祖先は中央アジアから北上し、10世紀初頭、バイカル湖の西側からレナ川に沿って北上し、レナ川中流域及びヴィリュイ川流域(中央ヤクーチヤ)に定着、その後、16世紀の帝政ロシア植民地化の開始と共に、レナ川下流、オレニョーク川、ヤナ川、インディギルカ川、コリマ川流域など北部ヤクーチヤに広がり、現在の分布域へと至った。
19世紀末には人口が20万人以上(そのうち、ロシア人は3万人)に達し、20世紀初頭以降、ロシアからの独立を主張するヤクート民族ナショナリズムが芽生え始め、ロシア革命直後には反ボルシェビキ勢力の一翼を担うこととなったが、1922年4月ヤクート・ソヴィエト社会主義自治共和国として、ロシア連邦の一部となった。
ソ連崩壊前の1990年9月、ヤクート自治共和国は国家主権宣言を発し、翌1991年12月の共和国大統領選挙。それと同時に共和国の名称が現在のサハ共和国(ヤクーチヤ)へと改称された。
ザバイカル地方
- 知事:
- アレクサンドル・オシポフ
- 議会議長:
- エン・フヴァ・コン
- チタ市長:
- イリーナ・シチェグロヴァ
- 地勢:
- 東シベリアに位置し、高山氷河地帯からツンドラ、ステップ、砂漠まで変化に富む様々な気候帯を抱えている。西はヤブロノイ山脈に囲まれ、南は中国及びモンゴルと国境を接している。
- 沿革:
-
16 世紀末に始まったシベリア開発に引き続き、 17 世紀半ばには、バイカル湖東部地域がロシア国家に統合されるようになった。このプロセスは 18 世紀初頭にほぼ完了する。
ザバイカル地域の開発に携わった移住者は2つのグループに分けることができる。1つめは、コサック、軍人、商人、手工業者、農民等のグループで、もう1つは、貧家や流民、シベリア流刑になった犯罪者等のグループである。この地域は、デカブリスト(農奴制と専制の廃止を目指して 1825 年 12 月に蜂起した貴族出身の将校たち)の流刑地としても有名である。
19 世紀初頭には人口も増え、 1851 年には、軍事力保持のため、バイカル湖からアムール川までの広大な領域にまたがる新しい行政区画、ザバイカル州が創設され、チタが州都となる。ロシア革命とそれに続く内戦期にチタを首都とする極東共和国の創設等の変遷を経て、 1937 年にチタ州が成立、同州が2008年にアギン・ブリャート自治管区と統合して、現在のザバイカル地方が形成された。
ブリヤート共和国
- 首長:
- アレクセイ・ツィデノフ
- 議会議長:
- ウラジーミル・パヴロフ
- ウラン・ウデ市長:
- イーゴリ・シュテンコフ
- 地勢:
- 東シベリアに位置し、北西にバイカル湖(湖岸の 4 分の 3 は同共和国に属す)を擁し、南西及び北東は山脈に囲まれた山がちな土地である。同国の最高峰は、ムンク・サルドィク山の 3491 m。南部はモンゴルと国境を接している。
- 沿革:
-
ザバイカル(バイカル湖以東)地域は、古代より中央アジアの歴史文化圏の一部であり、 1206 年には、チンギス汗が遊牧民の諸部族を大モンゴル帝国に統合。モンゴル帝国崩壊後も、分裂した形でこの地に遊牧民の諸部族は居住し続けた。
17 世紀、ロシアが国境を東に拡張し始め、ブリヤート族はモンゴル世界から分離されることになった。1666 年、ウダ川の岸辺にコサックにより建設された木造要塞が、その後、商人の街ヴェルフネウジンスクに発展し、現在のブリヤート共和国の首都ウラン・ウデとなった。
ロシア革命後の 1923 年、ロシア連邦を構成するブリヤート・モンゴル自治ソヴィエト社会主義共和国となったが、ソ連末期の1990年 10 月にブリヤート共和国は国家主権宣言を採択、 94 年には初代共和国大統領が選出された。
イルクーツク州
- 知事:
- イーゴリ・コブゼフ
- 議長:
- アレクサンドル・ヴェデルニコフ
- イルクーツク市長:
- ルスラン・ボロトフ
- 地勢:
- 東シベリア南部に位置し、東サヤン山脈及びスタノボイ高地(共に 3000 m級)等に囲まれ、面積は 76 万 7900 平方キロメートル(日本の約 2 倍)で、ロシア連邦全体の約 4.6 %(全国第 6 位)を占めている。
国土の約 80 %が針葉樹林(タイガ)に覆われ、北部には永久凍土地帯が広がる。また、東部には、世界の淡水量の5分の1をたたえ、世界一の貯水量と透明度を誇るバイカル湖が広がっている。 - 沿革:
-
イルクーツク市はロシア人によって 1661 年に築かれた城塞に起源をもち、その場所がイルクト川とアンガラ川の合流地点であったため、イルクト川にちなんでイルクーツクと名付けられた。
17 ~ 18 世紀には東西交易の接点となり、ロシア極東から毛皮、中国及びモンゴルから茶、絹などがヨーロッパへ、ヨーロッパ方面からは鉄製品や手工業品がアジア方面に運び込まれた。
帝政ロシア時代のイルクーツク市は反体制主義者・政治犯の流刑地としての長い歴史をもち、特に 1825 年に発生した「デカブリストの反乱」の首謀者たちが流刑された地として有名である。
1719 年に設立されたイルクーツク郡(その後、県)は、幾度かの変遷を経て、 1851 年に今日のイルクーツク州とほぼ同じ領域となり、 1937 年 9 月に「州」に改編された。